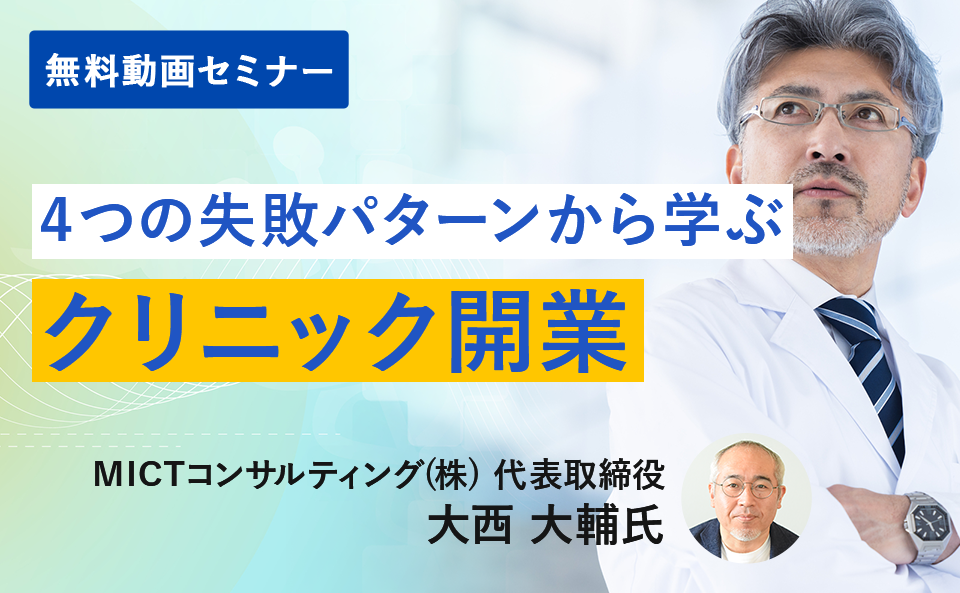メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-
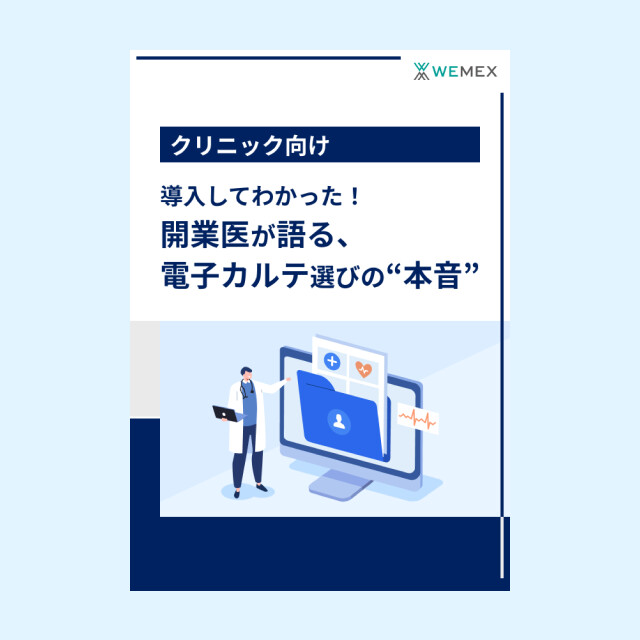
電子カルテ 医師 事務長
導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”
-
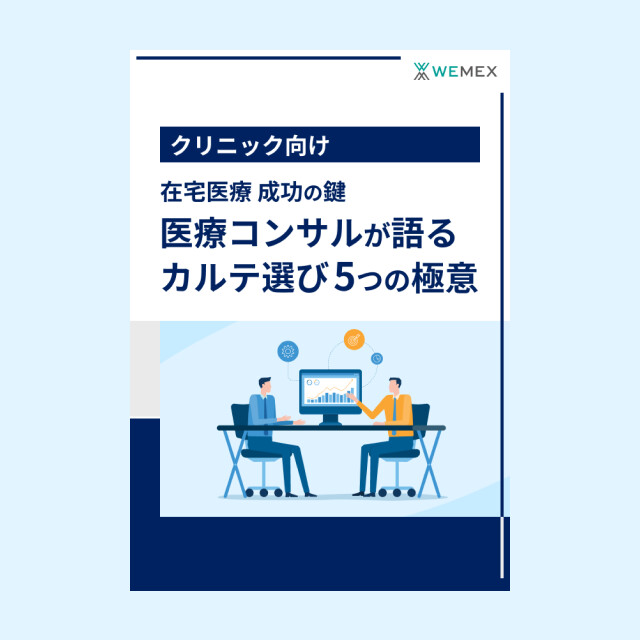
電子カルテ 医師 事務長
在宅医療成功の鍵 医療コンサルが語るカルテ選び5つの極意
-
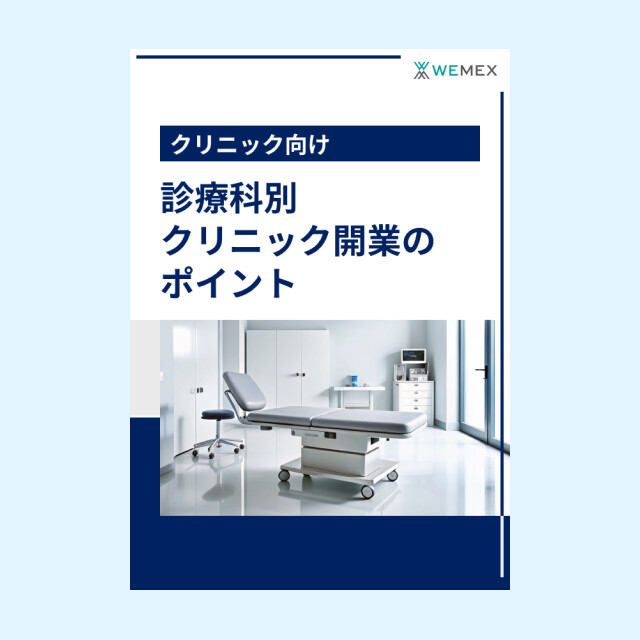
クリニック開業 医師 事務長
診療科別クリニック開業のポイント
-
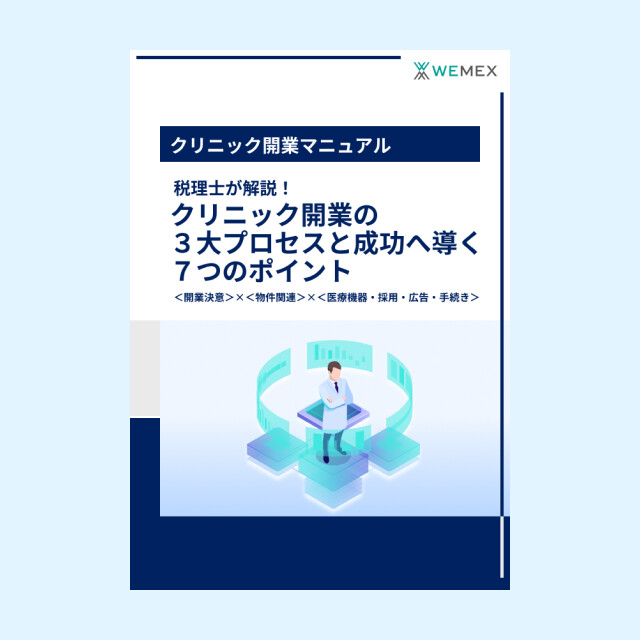
クリニック開業 医師 事務長
クリニック開業の3大プロセスと成功へ導く7つのポイント
-
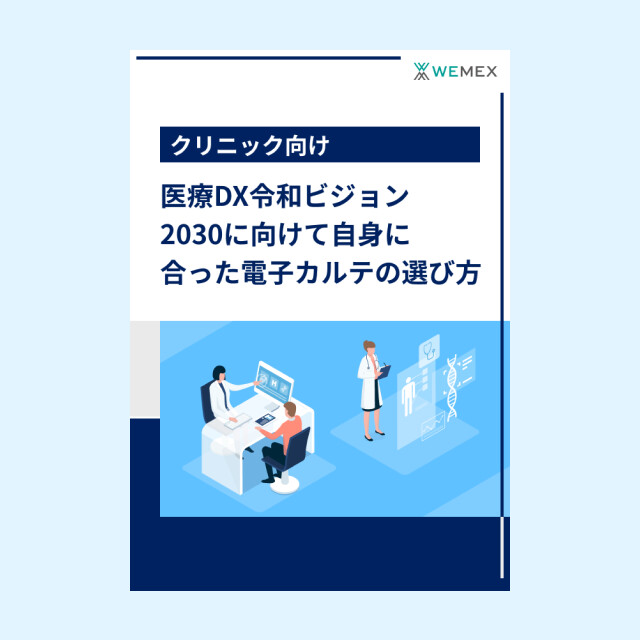
電子カルテ 医師 事務長
医療DX令和ビジョン2030に向けて自身に合った電子カルテの選び方
-
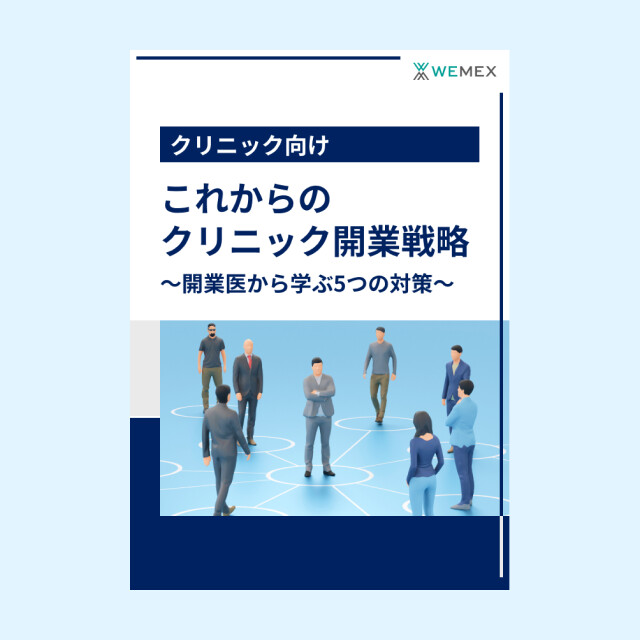
クリニック開業 医師 事務長
これからのクリニック開業戦略 ~開業医から学ぶ5つの対策~
-
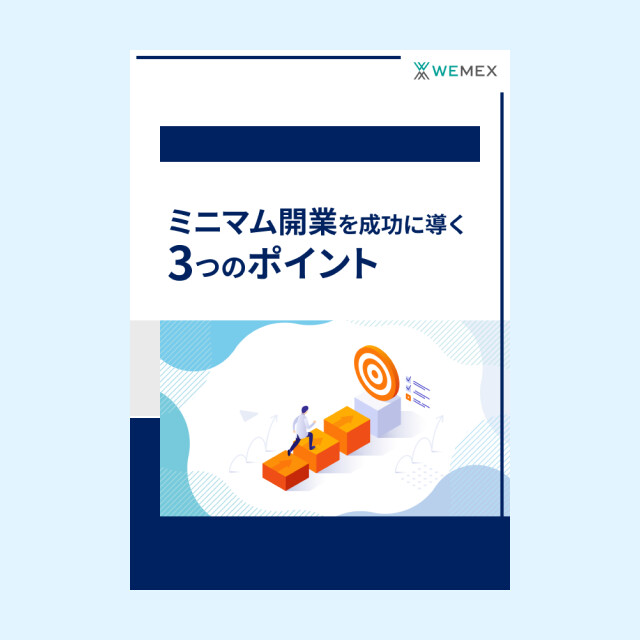
クリニック開業 医師 事務長
ミニマム開業を成功に導く3つのポイント
-
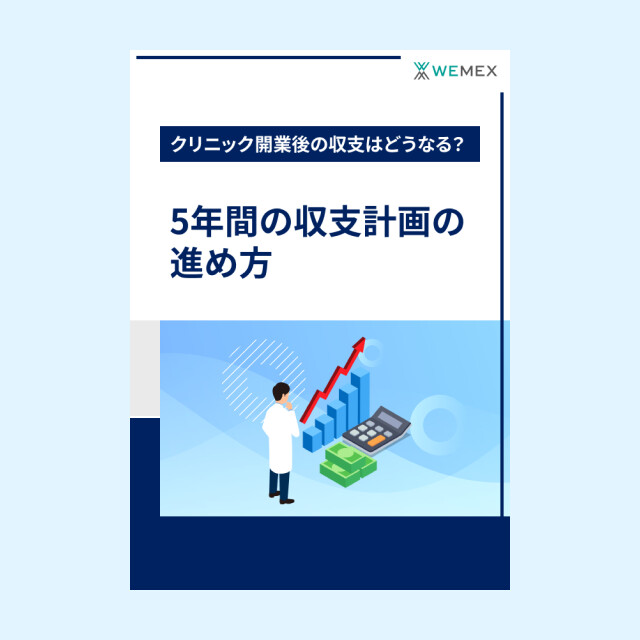
クリニック開業 医師 事務長
クリニック開業後の収支は?~5年間の収支計画の進め方~