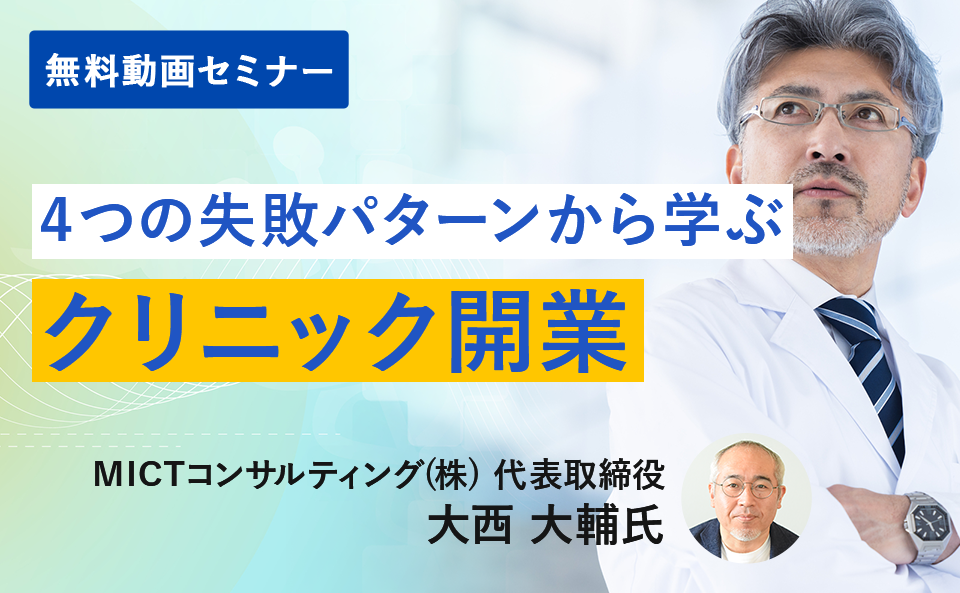目 次
1. コスト削減の鉄則
少子高齢化の影響に加えて新型コロナウイルスの収束の気配が見えず、病院を取り巻く経営環境はますます厳しさを増しています。地域や診療科によっても異なりますが、新型コロナウイルスの影響による受診控えや医療・介護の需給のアンバランスが大きくなっています。
ただ、新型コロナウイルスによる経営悪化といいますが、実は多くの医療機関の経営課題についてはコロナ禍以前から指摘されていたことです。コロナ禍は先延ばしにしてきた経営課題を顕在化したに過ぎません。
しかしもう先延ばしにはできません。これからの経営に危機感を抱いている病院の経営者の方に、経営改善につながるコスト削減の鉄則をわかりやすくご紹介します。
コスト削減といっても、医療機関は人の命を預かるところです。一般企業と同じように効率だけを優先することはできません。病院のコスト削減は単なる費用節約ではなく、医療の質を高めるためのコストの最適化を推進する活動です。 病院コスト削減のための3つの鉄則をご紹介します。
鉄則1:10人未満のプロジェクトチームで実施
コスト削減は、全院上げて行わなければ成果はでません。そのためには、医師、看護師、事務スタッフなど組織を超えた「プロジェクトチーム」で取り組むことが必須です。院長や理事長など経営陣を中心として、目的・目標・期限を明確にし、トップ直轄のプロジェクトにしなければ実効性はありません。人数は各部署を代表するメンバー10人以内とします。メンバーが当事者意識を持って各部署に持ち帰り実行するには、10人以内が最適です。
プロジェクトチームには、管理職だけでなく、看護師・医事課の現場スタッフを代表するメンバーも入れます。患者に日々接し、多職種と連携する看護師・医事課スタッフは改善のヒントを持っています。
鉄則2:コスト削減の目的を明確にする
コスト削減というと、スタッフは給与削減やリストラを心配しますが、人の問題に手をつける前に、できるコスト削減はたくさんあります。何のためにスタッフにコスト削減を求めるのか、最初にコスト削減の目的を明確にしましょう。
病院の存続のためとか、よりよい診療を提供するための資源集約とか、コスト削減の先の未来が見えてはじめてスタッフの意識が変わり、全院で取り組む体制ができます。
鉄則3:成果がわかる目標設定
コスト削減と言っても何でも削ればいいわけではありません。スタッフが業務を見直し、部署ごとにそして全院で何ができるか計画し、優先順位付けや取捨選択します。部署ごとに削減すべきコストを書き出した上で、具体的にコスト削減する項目と目標を設定します。
コスト削減術については以下のリンクも参考にご覧ください。
手段はいろいろ、コスト削減術
2. 病院におけるコストの特徴
病院におけるコストの特徴として、医療を提供するための医薬品費、レントゲンフィルムやガーゼなどの医療消耗品からなる直接材料費の割合が大きいことがあります。
また、医療機関の病床規模と診療科の構成によって大きく異なりますが、一般企業の人件費にあたる給与費の割合も比較的高い傾向があります。
病院でかかるコストの種類
病院でかかるコストは、主に下記のように分類します。
- ① 医薬・材料費
- ② 委託費
- ③ 給与費
- ④ 減価償却費
- ⑤ その他経費

「1. 医薬・材料費」は、医療提供の原価である直接材料費として、他の一般経費とは分けて考えます。医薬品費の他に、レントゲンフィルムやガーゼなどの消耗品の診療材料費、注射針や聴診器などの医療消耗機器備品費があります。
「2. 委託費」には、検査費、給食委託費、リネン委託費や事務委託費などが含まれます。
「3. 給与費」は、給与の他、社会保険料、福利厚生費や採用コストが含まれます。
「4. 減価償却費」は、設備投資した固定資産を耐用年数で除して毎年の費用とするものです。
「5. その他経費」は賃貸料や広告費など、①から④以外の経費全般です。
給料への不満は賃金労働者の大きな悩み
経費コントロールするとしても、給与カットやリストラは最終手段です。人手不足が進む中、一般的に医療機関では医療の質を維持しようとムリして働いているスタッフも少なくありません。さらに人員減などのコスト削減を行おうとすると、働くスタッフのモチベーションを大きく下げてしまい、「もうこれ以上はムリ」と医療の質を過度に下げてしまうことになりかねないので、注意が必要です。
3. 病院でコスト削減に取り組むべき費目
病院において経費コントロールする上で大切なことは「医療の質をできるだけ下げず」にコスト削減に取り組むことです。病院にとって、適切な医療を提供することは患者の生死に関わることであり最重要事項です。
優先的にコスト削減に取り組む項目として、下記の3つが上げられます。
ポイントは、医療の質を下げないこととスタッフのモチベーションに配慮することです。
(1)医療材料費の適正在庫
医療材料費については、医師の聖域としてコスト削減が難しいと思われがちですが、過剰在庫や使用期限切れの医薬品の廃棄損など、多くの病院で改善の余地があります。
主な削減方法は2つあります。
1つ目は、仕入れ単価の適正化です。病院では長年取引している医療卸業者と価格交渉をしないまま市場価格より高い仕入れ値で購入していたり、部署ごとに別々の卸業者から仕入れていたりすることがよくあります。市場の適正価格を確認した上で、院内の総発注数をまとめ卸業者と価格交渉を行うと、原価を下げることができます。
2つ目は、必要な医療材料の適正在庫量を決め、発注単位・頻度の見直し、在庫管理の手順を決めて全院で実施します。ムダな在庫や在庫管理の手間を減らすことで、労働時間の削減にもなり、医療材料費と給与費の削減効果が出ます。
(2)生産性向上による給与費削減
コスト削減としてのリストラや賞与カットは、働くスタッフのモチベーションを大きく下げてしまいます。ここでは、院内全体の生産性向上を意識して、2つの対策を検討します。
1つ目は、適正な人員配置を図ることです。
具体的には、看護補助者や医療クラークを雇用し、人件費の高い医師や看護師が本来の業務に集中できる環境を整備します。院内全体の生産性向上と時間外勤務を減らし、給与費を削減できます。
もう1つは、ITや院内の環境整備により、問い合わせや受付・案内の業務そのものを減らすことです。例えば、患者の問い合わせの多い診療時間や担当医の変更などの項目については、HPやLINEで最新情報の提供を徹底すると電話の問い合わせが激減します。同じように、院内で患者が迷いやすい複雑な移動経路について、床にわかりやすい誘導案内を行い、スムーズに移動できるようになり、対応スタッフ数を減らすことができます。
(3)設備管理費
病院の設備管理について、2つの事例を挙げましょう。
1つは、高度な医療機器の保守管理料の削減の事例です。
病院には、CTやMRIなど画像診断装置など高度な医療機器が多く、初期導入費に加えて、毎年の保守管理や修理費や滅菌管理などのメンテナンスコストが発生します。それを、「(A)部品代・技術料・訪問出張費」「(B)定期点検」「(C)消耗品」と3分類すると、(B)と(C)は医療機器を使用する上で必ず必要なコストですが、(A)については故障しなければ不要なコストです。これを保守契約とせずに、万一のリスク対応として、発生したときに損害保険でカバーする方法があります。保守管理料を数%軽減できる場合があります。
もう1つは、清掃費です。
新型コロナの影響で、清掃業務に従事する外国人労働者や高齢者の人数が減少し、清掃スタッフの確保が難しいため、価格交渉はあまり期待できません。清掃コストの削減として、清掃の頻度を下げる方法があります。例えば、汚れがつきにくい素材へ変える、表面に防汚加工を施す、床のワックスに代えて防汚効果の高いコーティングを行うなど、清掃頻度を変えて外部委託の清掃費を下げた事例があります。
病院コストの削減(固定費の場合について)
固定費は、患者がこなくても固定的にかかる費用です。大きいのは給与費と賃貸料などです。給与費の中では、単価の高い非常勤勤務医が多いと給与費が大きく膨らむ傾向があります。診療曜日と時間帯の集約で非常勤の勤務時間を減らす、常勤医を採用する、採用コストを下げるなどを検討します。
賃貸料については、新型コロナの影響で賃貸物件の賃料が下がっています。賃貸料や駐車場費用の価格交渉はやってみる価値があります。
病院コストの削減(変動費の場合について)
変動費は、医療収益に比例してかかる経費で、主に医薬・材料費や委託費です。変動費として、パートスタッフや送迎費を計上している例もありますが、患者数が減ってもシフト上、スタッフを減らすことができず、実際には固定費用になっている場合も少なくありません。医薬品・委託料以外は、実質、固定費と考えて経費削減を考えることをお勧めします。
4. 経費をコントロールする上でのポイント
医療の専門家である、医師や医療従事者は医療の質優先でコスト意識が低いことと変革を好まない特性があるため、医療の質に関わる医薬品や医療機器に関するコスト削減を図るのは簡単ではありません。
また、病院は、医師・看護師・医療専門職と医療事務からなる縦割り組織であるため、全院体制でコスト削減に取り組むには、組織横断的に目的を理解し、ゴールイメージを共有することが大事です。
コスト削減といえばマイナスイメージを持ちがちですが、医薬品や医療機器のコストの見直しやスタッフの効率的な配置をすることで、医療の質を落とさずに、より収益の高い診療への集約や労働時間が減り働く環境が改善などのプラス効果を見える化するとスタッフの経費削減への意識が変わります。
5. 病院におけるコスト削減の具体的な手順
(1)経営課題を抽出する
コスト削減に取り組む前に、プロジェクトチームで全院の経営課題の抽出を行います。診療報酬改定への対応の遅れ、人員過不足や非効率な配置、施設の老朽化、地域の医療需要の変化に対応していないなど、経営悪化の原因は様々です。経営状態の現状把握と改善に向けての検討をした上でコスト削減を行います。
(2)現状のコスト分析から始める
最初にすべきことは、収支の現状を把握しコスト分析を行います。病院でかかるコストの種類で記述した①から⑤の費用と⑤の中でも、賃貸料と広告費などの主な費用に分類した上で、診療科別に各費用の売上対比出します。数字だけを見ていても実態は把握しにくいのですが、過去3年の売上対比、診療科ごとの比較、同じ規模の診療科との比較など、比べることで違いが見えてきます。数字だけでなくグラフにして見える化することも効果的です。
現状を把握しないまま、やみくもにコスト削減に取り組んでも効果はでません。
(3)リストアップ
コスト分析の後は、取り組み候補項目をリストアップします。全院で取り組むこと、各部署で取り組むことに分け、医療材料や委託の見直しなどのコスト削減策を具体的にリストアップします。細かいことでも探せば改善項目はたくさんあるでしょう。
(4)優先順位をつける
コスト削減と言っても、医療収益を上げるための経費とそうでない経費は性格が違います。コストを下げようと、広告費や研修費まで一律に下げてしまうと、新患者数が減ったり医療サービスの質が下がったりします。結果として経費削減できても、医療収入も減ってしまっては元も子もありません。
リストアップされた取組を「時間軸(すぐできる・時間がかかる)」「コスト軸(コストがかからない・かかる)」「医療の質(上がる・下がる)」「インパクト(効果が大きい・低い)」などの軸で分け、優先順位を検討します。
(5)行動計画と目標設定
コスト削減の目的を達するため、全院と各部署の取り組み内容を決め、行動計画と数値目標を立てます。確実に目標達成するためには、目標設定時に「5つの要素」を決めて各部署で共有して実行すると効果的です。5つの要素は、その頭文字から「SMART」の原則と呼ばれます。
1:Specific(具体的に)
誰でもわかる具体的な言葉で書き出します
例)看護師でなければできない仕事以外は看護補助者に任せる
2:Measurable(測定できる)
達成度合いが測定できる目標を決めます
例)看護補助者が一人でできる業務を4段階で測定する
3:Achievable(達成可能な)
頑張れば達成可能な現実的な目標数値を立てます
例)看護師から看護補助者に移行する業務数を30とする
4:Related(関連した)
全院で決めた目的に関連した目標を立てます
例)看護補助者を導入し、看護師の時間外労働を削減する
5:Time-bound(期限を設定する)
いつまでに目標達成するか、期限を設定します
例)今年度内に達成する

目標は自分たちでコントロールできる項目を決めます。例えば、看護師の時間外労働を10時間削減すると言っても具体的に何をすればいいかわかりません。結果指標でなく、行動指標を決めて実行することが大事です。
(6)成果
行動目標を決め実行したら、その成果を検証し共有します。その上で、次に取り組む課題や取り組み方法の改善を検討します。
例えば、上の例では、「看護師の時間外労働を削減する」という目標に対して、看護補助者を育成し、看護師の業務の内、30業務を看護補助者に移行した結果、看護師の時間外労働時間がどのくらい減少したかを確認します。
コスト削減も目的を共有し、全院で何のためにやるかを納得した上で取り組み、その成果を確認し、取組方法を改善する、そのステップを繰り返します。マイナスのイメージでやらされ感で取り組むのと比べ、成果が出てスタッフの意識も変わります。
筆者プロフィール
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-
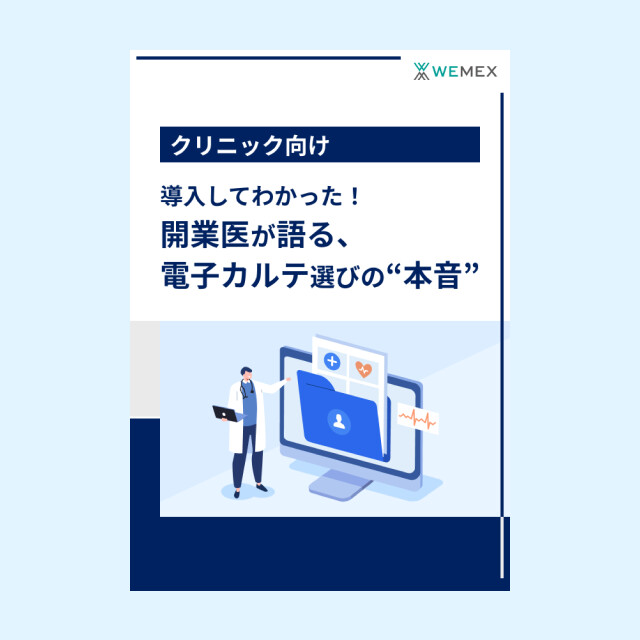
電子カルテ 医師 事務長
導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”
-
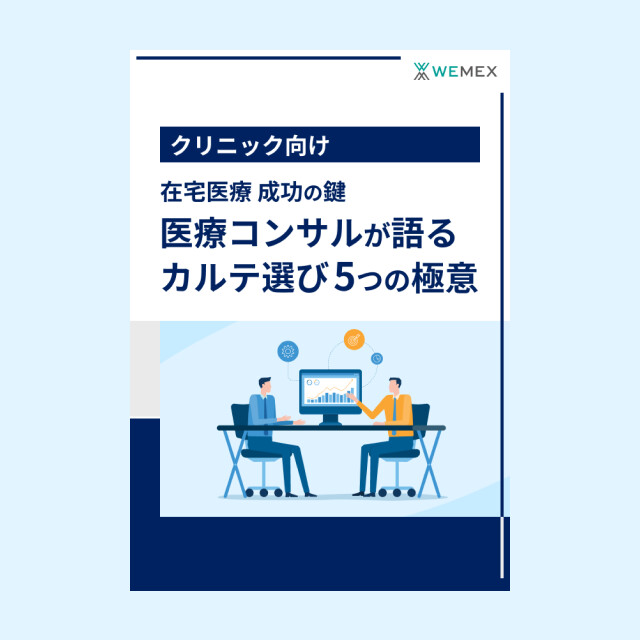
電子カルテ 医師 事務長
在宅医療成功の鍵 医療コンサルが語るカルテ選び5つの極意
-
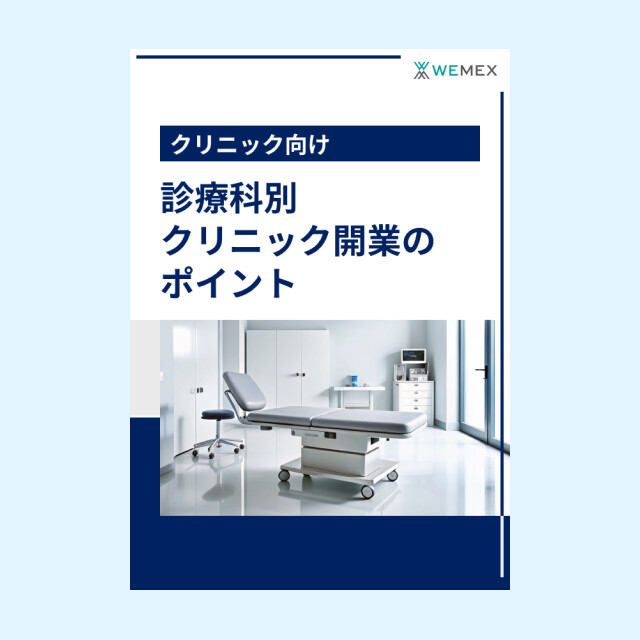
クリニック開業 医師 事務長
診療科別クリニック開業のポイント
-
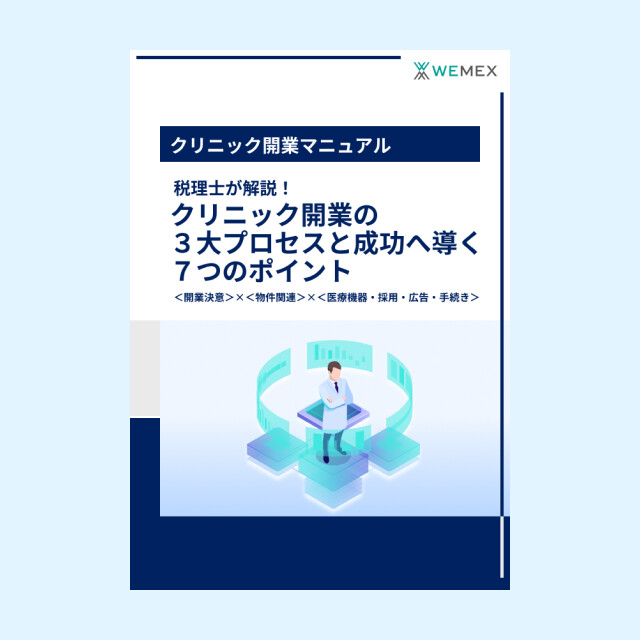
クリニック開業 医師 事務長
クリニック開業の3大プロセスと成功へ導く7つのポイント
-
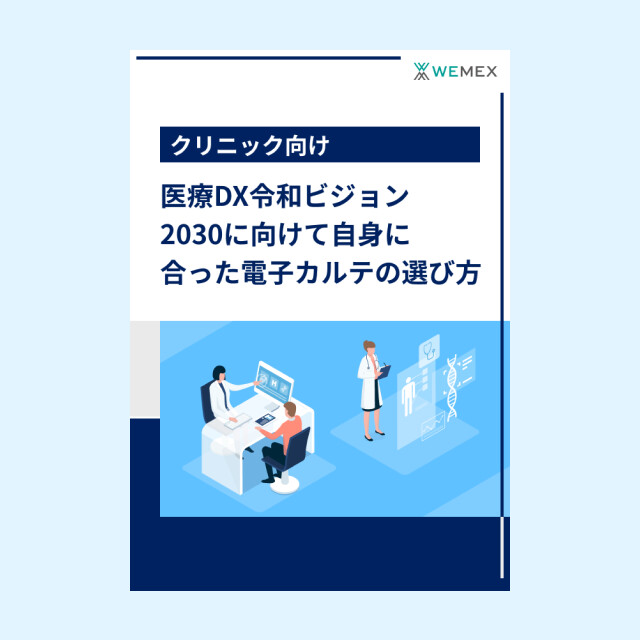
電子カルテ 医師 事務長
医療DX令和ビジョン2030に向けて自身に合った電子カルテの選び方
-
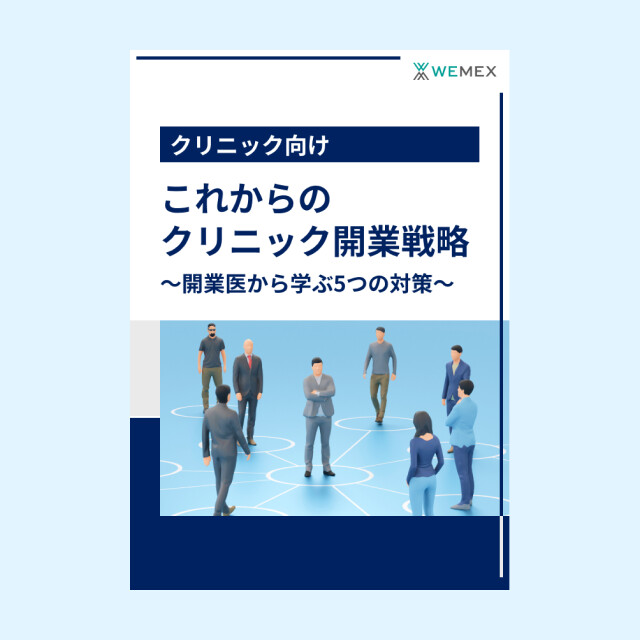
クリニック開業 医師 事務長
これからのクリニック開業戦略 ~開業医から学ぶ5つの対策~
-
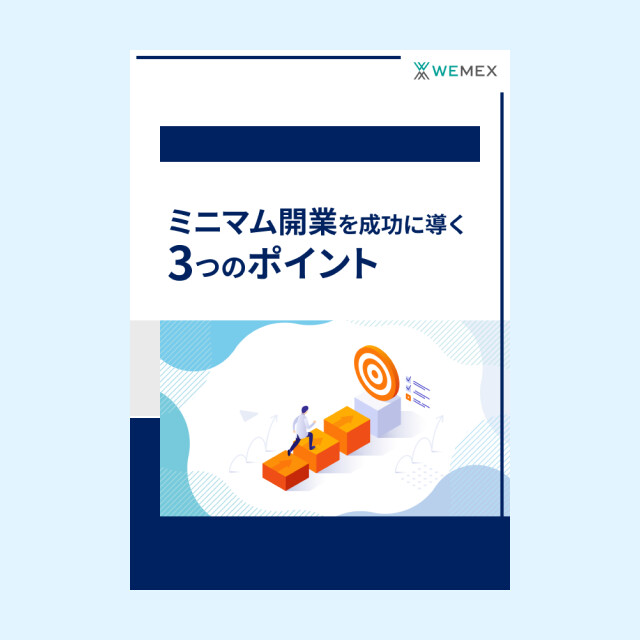
クリニック開業 医師 事務長
ミニマム開業を成功に導く3つのポイント
-
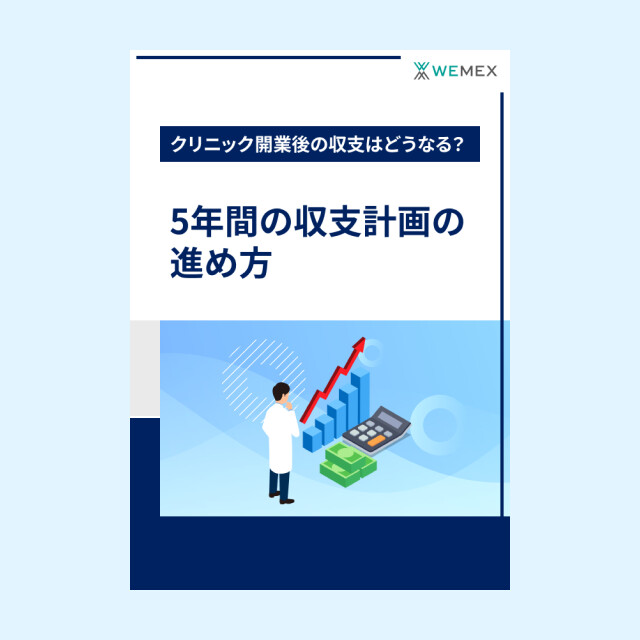
クリニック開業 医師 事務長
クリニック開業後の収支は?~5年間の収支計画の進め方~