目 次
1. 必須資格は医師免許のみ
クリニックの開業に必要な資格は、医師免許です。実際には、開業する人が医師でなくても、医師または歯科医師の免許を持つ人が管理者として院長になれば、開業はできます。年齢制限もありません。
そのほかの資格は必須ではありませんが、あると役に立つ資格がいくつかあります。
1つは、医師の専門性を示す「専門医」の資格です。2年間の「初期臨床研修」で基礎的な臨床能力を身につけた後、後期研修として専門医の資格取得を目的に後期研修を受けます。「初期臨床研修」を終えた9割の研修医が、「専攻医」を目指し、各病院が運営する専門医プログラムに参加しています。
ほかにも、クリニックを経営するのに役に立つ経営能力を身につける資格があります。医療機関の経営に関する資格はいくつか民間資格がありますが、クリニックの経営に特化したものは少なく、診療科や規模によって経営形態も違います。医療機関の経営について学び、資格を取得してもすぐ実践的に役立つとは限りませんが、経営能力を高めることは必要です。
そして、クリニックの施設管理者として必要な資格です。具体的な資格の例は、以下で解説します。
2. 開業時に持っていると役に立つ資格と取得方法
クリニックの経営能力に関する資格としては、いくつか民間の資格があります。「医療経営士」や「医業経営コンサルタント」、「病院経営管理士」などです。また、最近では、医療に限らず経営力をつけるため、経営学修士(MBA)や国家資格の中小企業診断士などの資格を取る医師も増えています。
(1)医療経営士
「医療経営士資格認定試験」は、医療機関の経営を担う人材育成を目的に、2010年に設立された一般社団法人日本医療経営実践協会が実施している試験制度です。医療および医療経営の基本を身につける3級から経営幹部として意思決定できる1級までの3等級に分けて認定試験を行っています。
2021年現在、3級、2級、1級合計で約12,500人の「医療経営士」が活躍しています。医師を想定した1級の合格者は110名、うち病院勤務者は4割ほどです。ほかは医療機関を顧客に持つ医療機器や医薬品会社などの医療関連企業や金融機関勤務者が合格し認定を受けています。
[資格取得方法]
3級は誰でも受験できます。2級受験の必須条件は、3級合格後に日本医療経営実践協会に「正会員」として登録していることです。3・2級はマークシート形式です。
1級受験の必須条件は、2級に合格し「医療経営士2級 正会員」として登録していることです。認定を受けるには、記述式の第一次試験合格後、口頭試問・個人面接の第二次試験に合格する必要があります。
試験対策としては協会推薦の試験対策テキストがあり、試験対策講座が行われています。
(2)医業経営コンサルタント
「医業経営コンサルタント」は、1990年設立の公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会の認定資格です。2021年現在、約3,000名の資格取得者がいます。
クリニックや病院など医療・介護施設向けの経営コンサルタント資格ですが、資格取得後も継続研修の履修が義務付けられ、資質と能力の向上を図ることができるため、病院勤務医やクリニック開業医師の資格取得者も増えています。
[資格取得方法]
協会主催の指定講座を受講し、一次試験(筆記試験)と二次試験(論文審査)に通ったのち、協会の正会員となることで認定登録が完了します。
なお、医業経営コンサルタント協会で実施している「一般公開 医業経営実務講座」は、医療機関勤務の事務部門、看護部門・コメディカルの方を対象、「医業経営管理能力検定」は大学生等を対象としています。
(3)病院経営管理士
「病院経営管理士」は、1951年設立の一般社団法人日本病院会による認定資格です。
この資格は、病院の事務長育成を目的に実施している同会の「病院経営管理士通信教育」の卒業生を対象に付与されます。2019年現在で、1,110名(第41回認定まで)が認定登録されています。
この通信教育は、医師対象というわけではなく、病院経営に関わる全職種を対象に募集しています。カリキュラムは、医療に関する科目、経営管理に関する科目、経営管理演習と幅広く、講師陣は各分野で活躍する病院理事長や医師、大学教授などが勤めています。
[資格取得方法]
一般社団法人日本病院会の「病院経営管理士通信教育」を2年間で受講し、医療関連科目、経営管理科目、経営管理演習、特別講座、卒業論文まで39科目を修了すると、日本病院会認定「病院経営管理士」として登録されます。
参考:一般社団法人日本病院会HP
参考:一般社団法人日本病院会「病院経営管理士通信教育」
(4)防火管理者
「防火管理者」は施設管理者として必要な資格です。消防法に基づき、建物の用途、居住または勤務する人、収容人数によっては、防火管理者を選任しなければなりません。テナントとして入居するビルの収容人数が30人以上であれば、防火管理者が必要となります。
開業前に、所轄の消防署に「防火管理者選任届」と「消防計画書」など所定書式の届け出が義務付けられています。
防火管理者の資格取得は、医師ではなく事務長やスタッフでも構いません。しかし、スタッフは退職する可能性もあるので、通常は開業前に医師が防火管理者の資格を取っておくことが望ましいです。
防火管理者の仕事には下記のようなものがあります。
- 火災発生時の対策を定めた消防計画を作成する
- 日常の火気管理の徹底や消防用設備の点検管理を行う
- 火災に備えて避難訓練や消火訓練などを行う
[資格取得方法]
一般社団法人日本防火・防災協会が実施する防火管理者講習を受け、講習後の効果測定に合格することで、取得できます。

3. まとめ
クリニックを開業するのに医師免許以外の資格は必要ありません。でも、開業後、経営を持続させ、地域になくてはならないクリニックとして存続し続けるには、医師としての知識・資格だけでは不十分です。
経営や組織面でどんなクリニックにするのか、開業前から中長期的な目標を決めて、スタッフとビジョンを共有し、風通しの良いチームを作ることが大事です。クリニックにありがちな縦割りの属人的な業務分担から、全員が院内全体を俯瞰し効率の良い働き方ができるようになると、生産性も上がりコスト削減につながります。そして院長がすべてを抱え込むことなく、クリニック経営の右腕となるスタッフ育成を計画することも有効です。
筆者プロフィール
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-
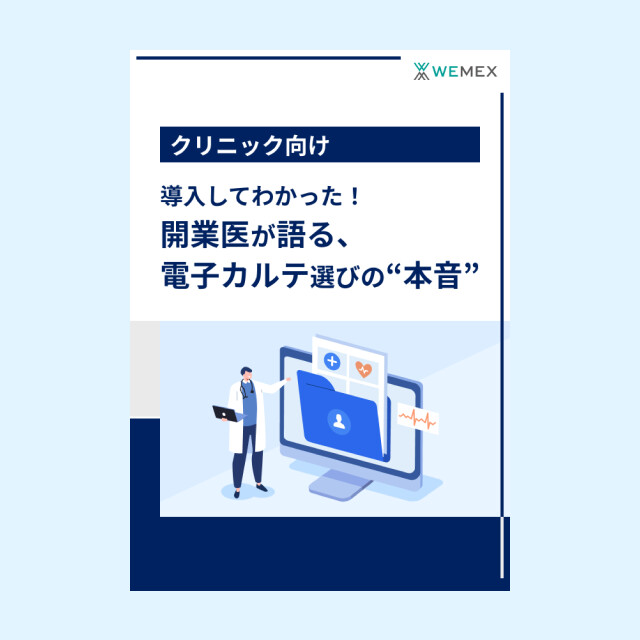
電子カルテ 医師 事務長
導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”
-
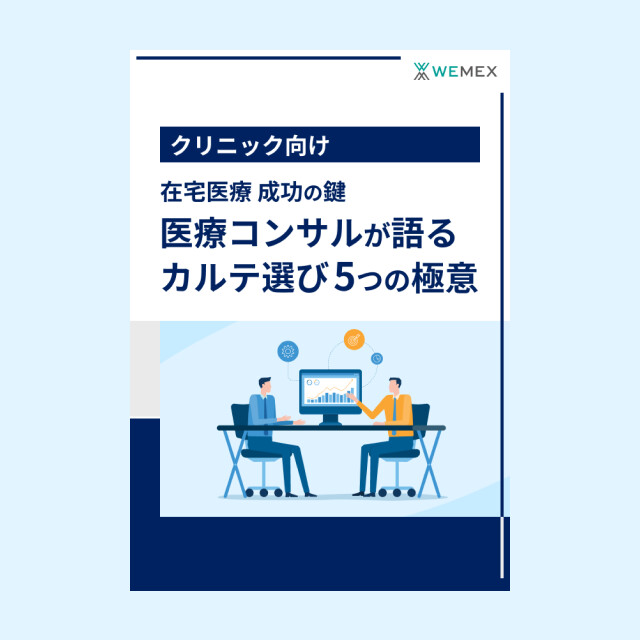
電子カルテ 医師 事務長
在宅医療成功の鍵 医療コンサルが語るカルテ選び5つの極意
-
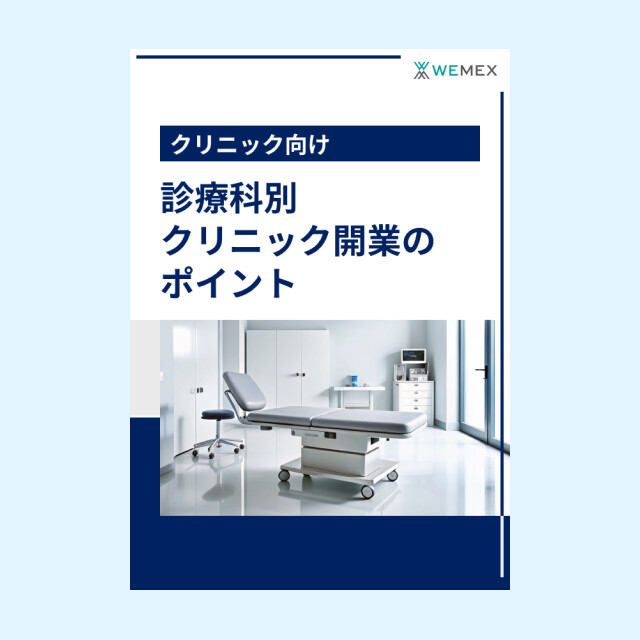
クリニック開業 医師 事務長
診療科別クリニック開業のポイント
-
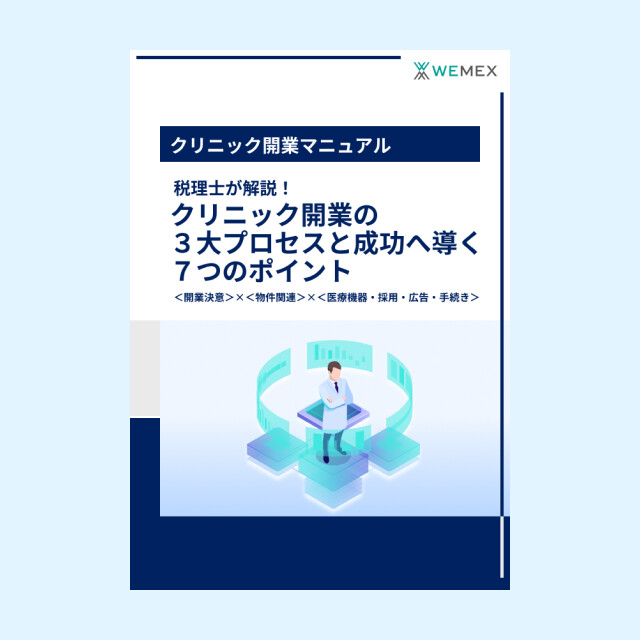
クリニック開業 医師 事務長
クリニック開業の3大プロセスと成功へ導く7つのポイント
-
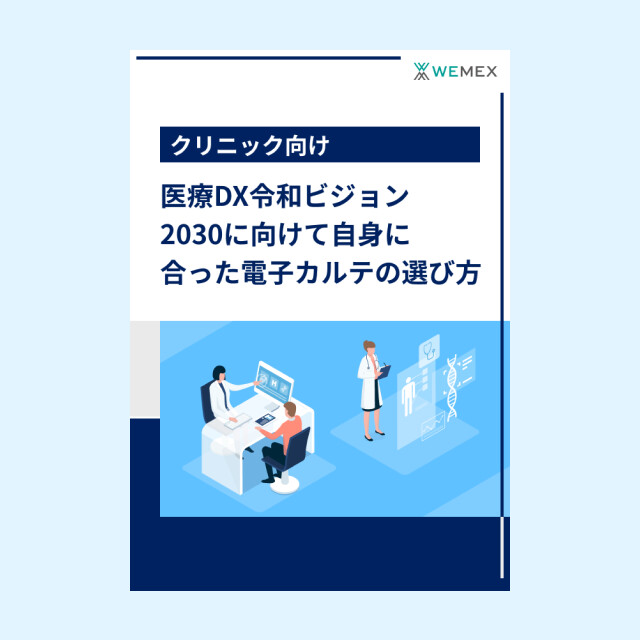
電子カルテ 医師 事務長
医療DX令和ビジョン2030に向けて自身に合った電子カルテの選び方
-
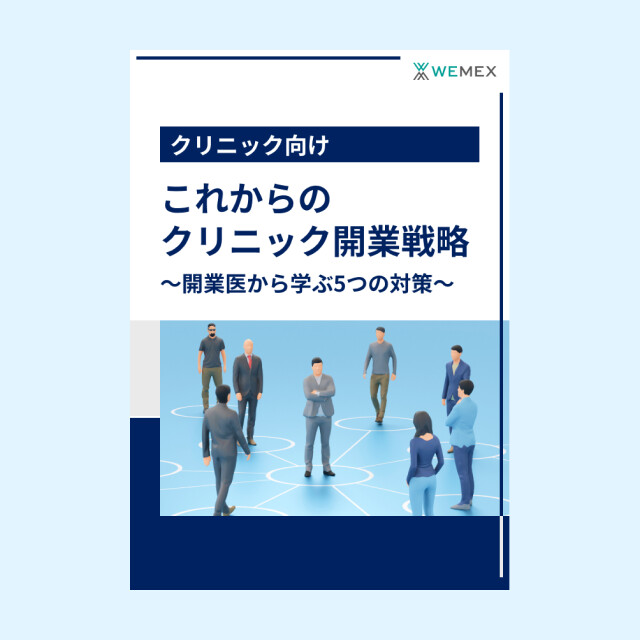
クリニック開業 医師 事務長
これからのクリニック開業戦略 ~開業医から学ぶ5つの対策~
-
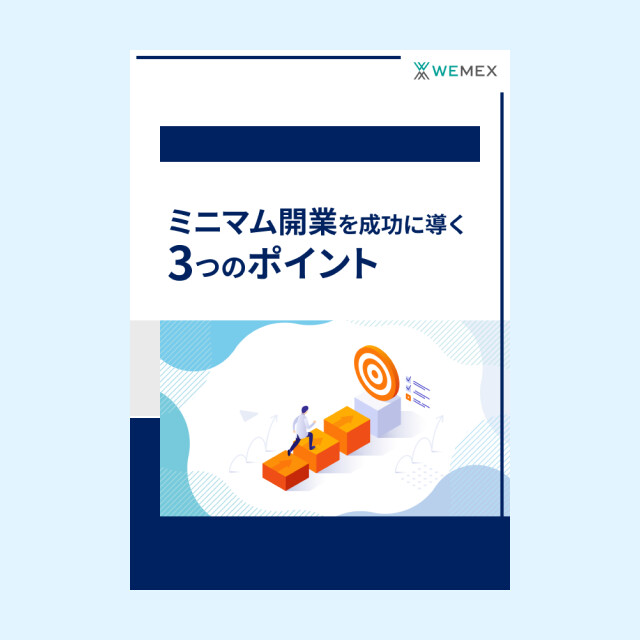
クリニック開業 医師 事務長
ミニマム開業を成功に導く3つのポイント
-
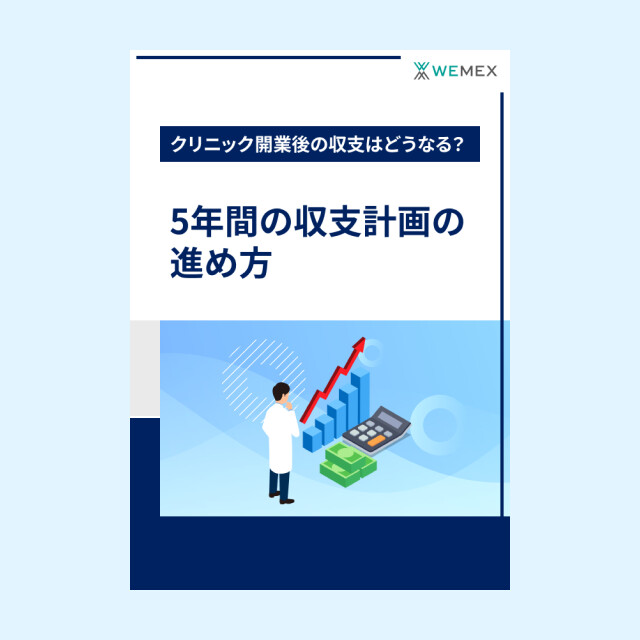
クリニック開業 医師 事務長
クリニック開業後の収支は?~5年間の収支計画の進め方~






