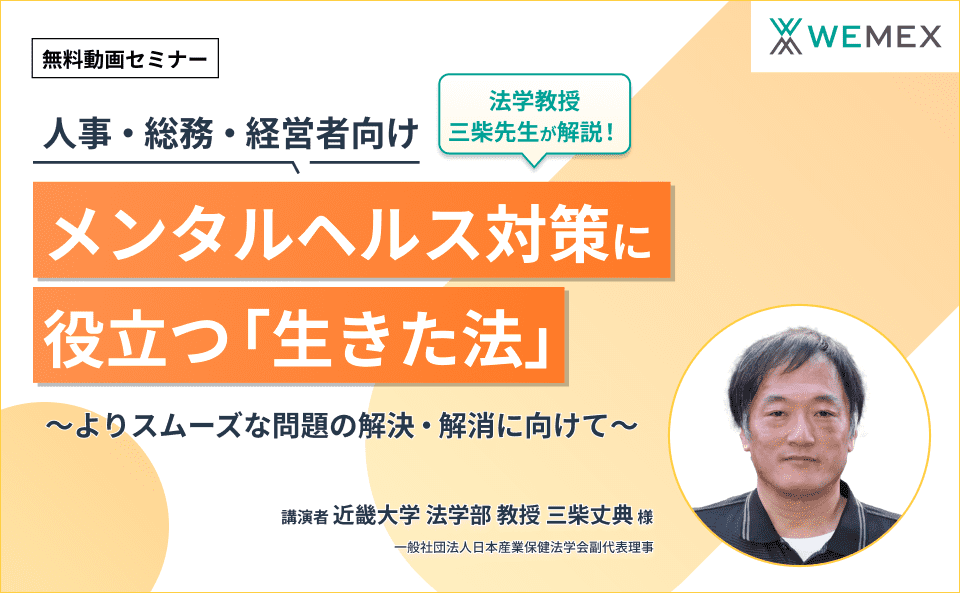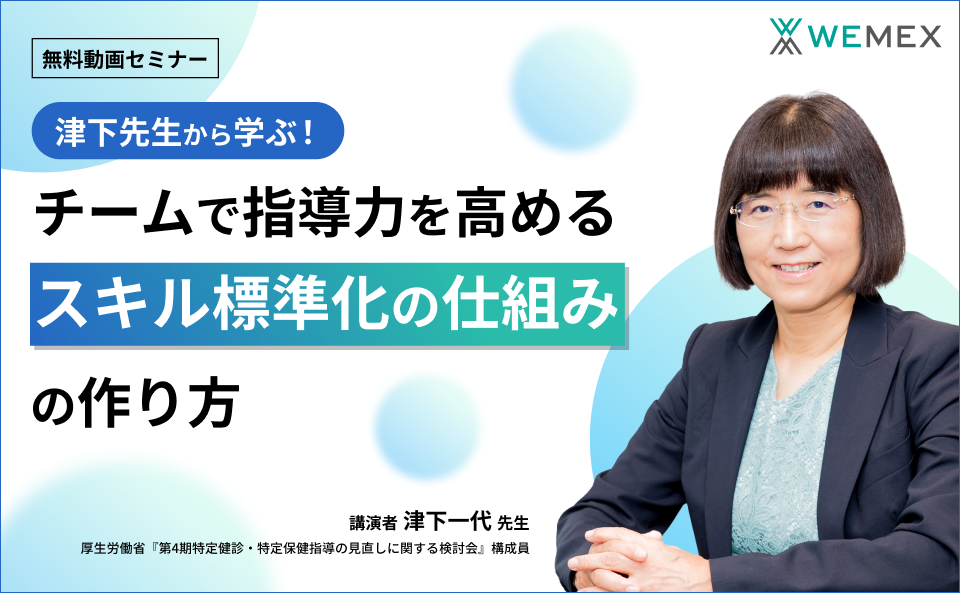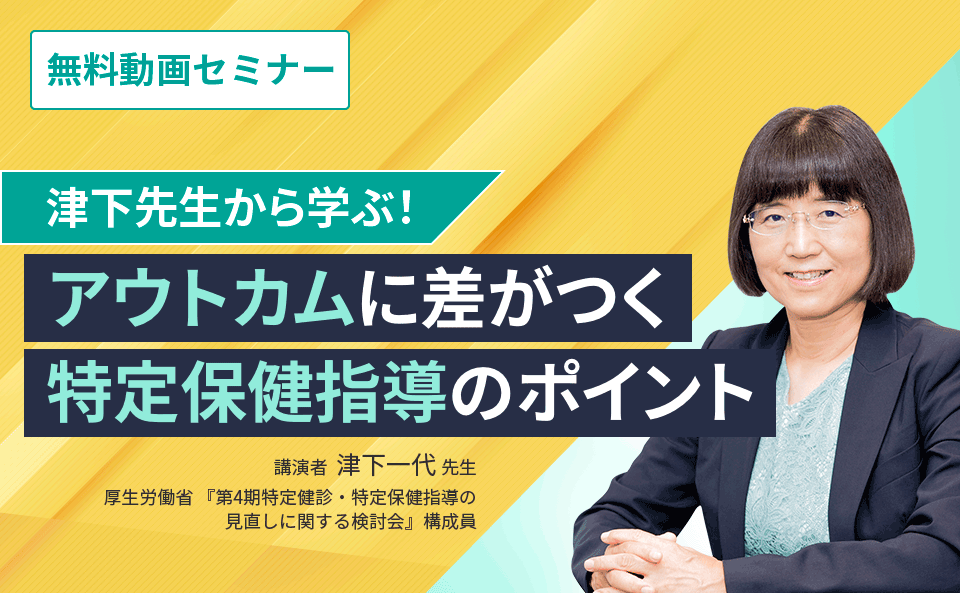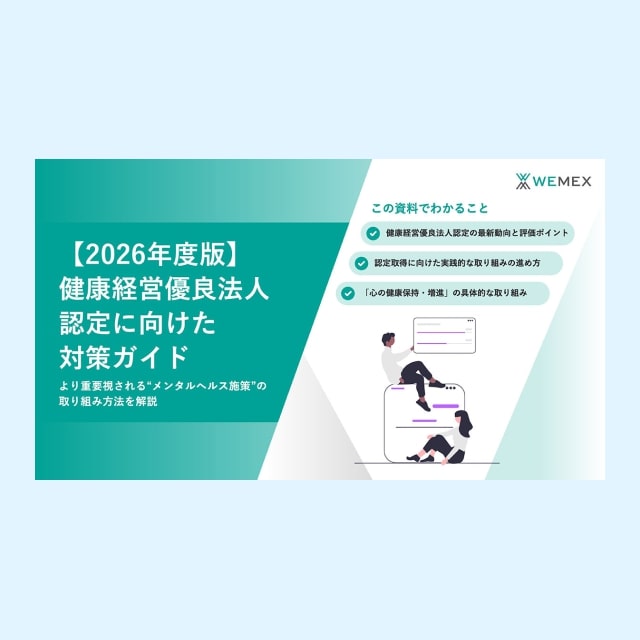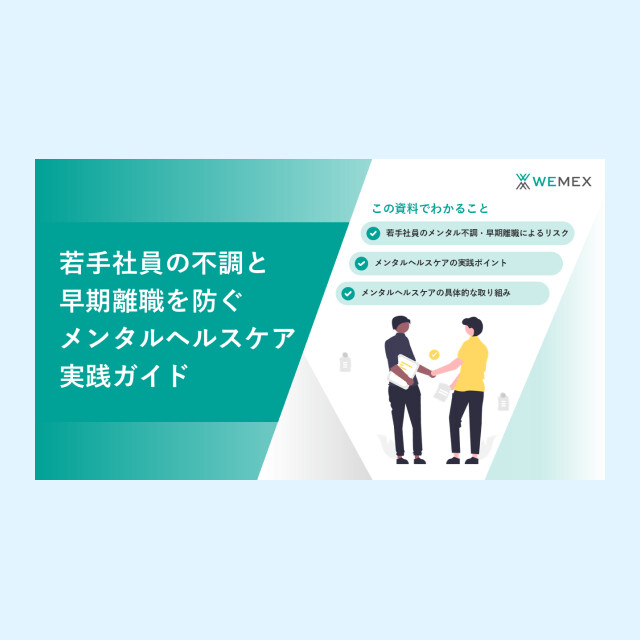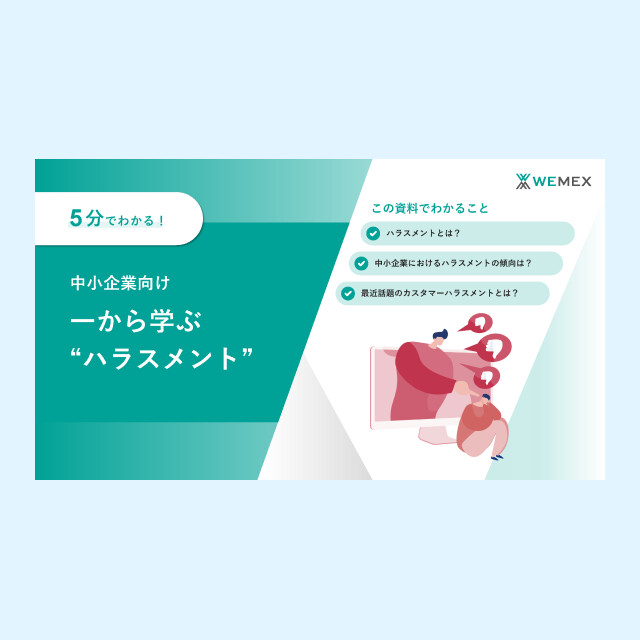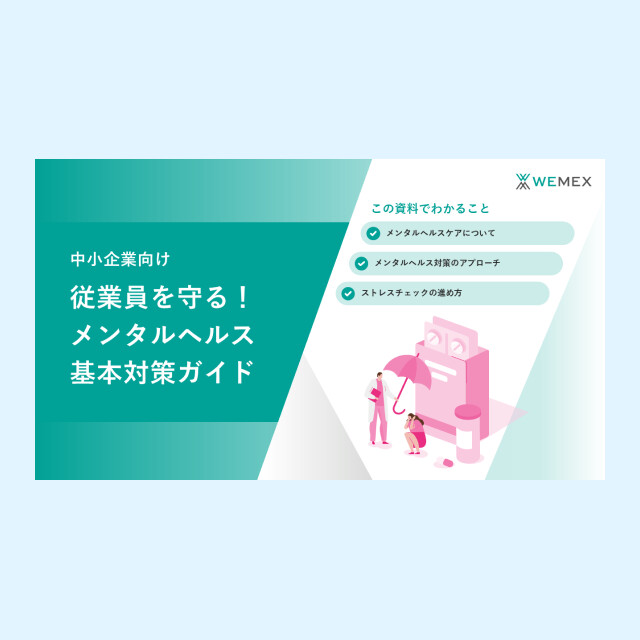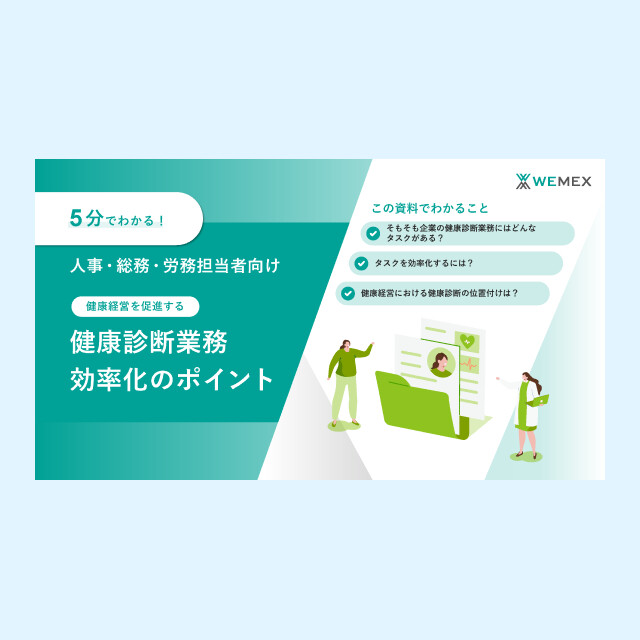【津下先生解説】特定保健指導対象者の離脱を防ぐ、支援時に必要な〇〇とは? vol.8
第4期特定健診・特定保健指導制度が2024年4月から開始されました。ウィーメックスは指導品質の向上のためのセミナーを開催し、第1期より厚生労働省等の検討会委員を務めている女子栄養大学特任教授の津下一代先生に解説いただきました。本コラムでは、講演内容のポイントをさらに詳しく解説いただき、連載でお届けいたします。今回は2024年3月7日開催のセミナーから、対象者と信頼関係を築く際の留意点について教えていただきました。
※本内容は公開日時点の情報です
目次
Q1.保健指導に後ろ向きな方を面談で前向きにできたのですが、その後体重が増加し「効果がない」とご自身で判断され脱落された方がおりました。指導者としてどのような事に注意する必要があったか、サポートする上での着眼点を教えてください。
A.保健指導でやる気になってもらったと思ったのに、思わしい結果につながらなかった。ここで落胆する気持ちのまま終わらせず、気持ちを落ち着けて原因や対処法を考えられるのは、保健指導者として成長のあかしです。私も、限られた条件から頭を悩ませてみました。
「後ろ向き」の方が「前向き」になったことから考えられることは?
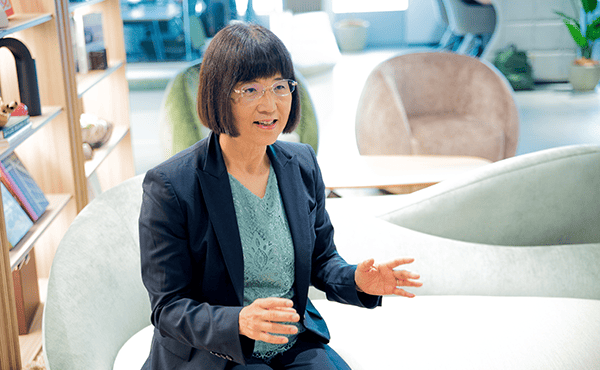
面談により気持ちが前向きになり、目標設定にまでつながったようです。しかし、もともと「後ろ向き」だったことは、行動変容への準備度が低かったことを意味します。生活をどう改善したいか、どんなことならできそうか等のイメージをもてないまま、保健指導者の勧めのとおり、行動目標を立てたのかもしれません。
対策としては、目標設定の際に「これはあくまで机上の目標なので、やってみて自分の生活に合った方法に修正が必要かもしれない」、「次回の相談時に状況を教えてほしい」と伝えてみてはいかがでしょうか。「保健指導で立てた行動目標」が「本人自身の目標」となり定着するためには、やってみながら考える時間、できなかった体験も含めて、本人の体験や考えが十分に反映されることが大切です。その経験を共有することにより、実効性の高い目標設定や効果的な支援につながっていきます。
「その後体重が増加し『効果がない』とご自身で判断」したことから考えられることは?
「効果がない」と判断したということから、何らかの行動を起こした可能性が考えられます。期待するほどの効果がなかったため、継続への意欲が減退したのかもしれません。
対策としては、「その行動を実行することで、どのくらいの減量効果が出そうか」と、「本人の減量への期待感」のすり合わせを行うことです。
例えば、毎日約20分間余分に歩くことは本人にとっては大きな努力ですが、エネルギー消費量は50kcalに満たず、1ヵ月行っても0.2㎏程度のわずかな減量にとどまります。「たったそれだけ~」と感じるなら、もっと大きな減量目標に到達できるよう、エネルギー摂取量の減少も加えた目標設定につなげます。本人の期待する減量効果とつり合いが取れていないと、落胆させる(信頼をそこなう)ことになるからです。
保健指導では、取り組みやすさの観点から、負担感の小さい目標を推奨することがあるかもしれません。その場合には、小さな減量でも、たとえ行動の変化だけでも、健康上の効果があることをしっかりと伝え、体重がすぐには減らなくてもあきらめないことを伝えるとよいでしょう。
「自身で判断し、脱落した」ことから考えられることは?
体重が増加したことを失敗ととらえ、成功の見込みはないと考えて脱落したのかもしれません。そんな時こそ、後ろ向きの気持ちを前向きに変える保健指導の役割がありそうです。できないことも含めて安心して相談できる雰囲気づくりに努める必要があります。
アウトカム重視の方向ではありますが、保健指導者が体重減量という成果を焦らないことも大切です。生活習慣の見直しにも着目して、できていること、小さな変化を一つでも発見し、フィードバックを心掛けるとよいでしょう。
Q2.健診を受けたら良しとしている方が多く、生活習慣を変えようとされない方が耳を傾けてくれないことに悩んでいます。このような方に、ご自身の健康に関心を持ってもらうためのテクニックはありますか。
A.結果表は数字の羅列であり、パッと見て面白いものではないかもしれません。また、医師が結果を判断し、治療の必要な人を発見するというイメージが強いのかもしれません。
しかし、特定健診は動脈硬化に関連する検査がほとんどで、項目数も限られています。一般の人にとっても、毎年の結果を比較することで、「体の声を聞くことができる」すぐれものです。
体重の変動を反映する項目(中性脂肪、GPTなど)や、本人が気にしている病気に関する項目(血糖、血圧等)に着目して、どのような機序(メカニズム)で悪化・改善するのか、イラストを見せながら説明するとよいでしょう。データが悪化したり、基準値を超えてくるなどの変化があった場合には、軌道修正のタイミングであることを伝えます。本人がイメージしやすいように、図やたとえを使うことも効果的です(詳しくは別の機会に・・)
鉄道は毎日点検をして、少しでも問題があれば修復します。早期発見と早期修復により事故を未然に防いでいます。健診も体のメンテナンスに活用してほしいと思います。
▽前回のコラムをご覧になりたい方はこちら
https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/healthmanage-point-07
▽関連資料
『対象者と信頼関係を築くためのスキルの習得』
https://go.medicom.phchd.com/wellsportstep_seminar_material_20240307(PDF)