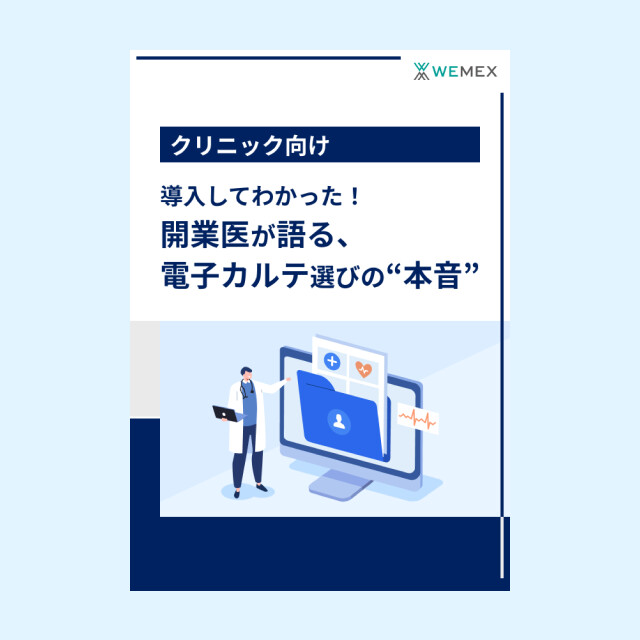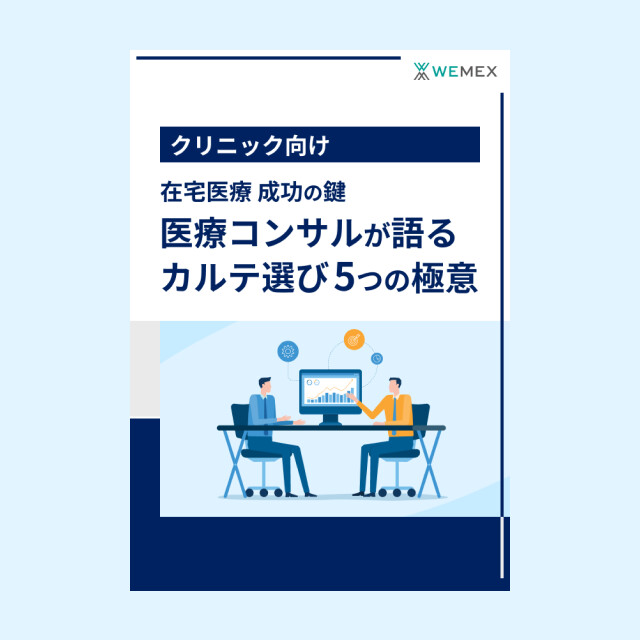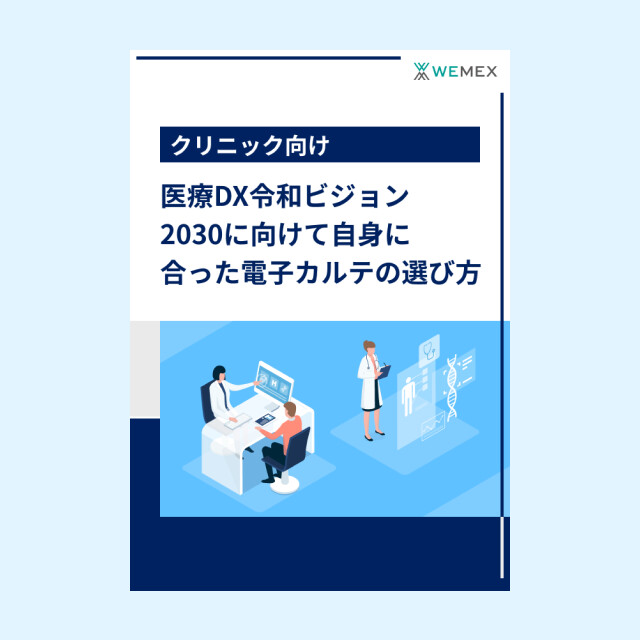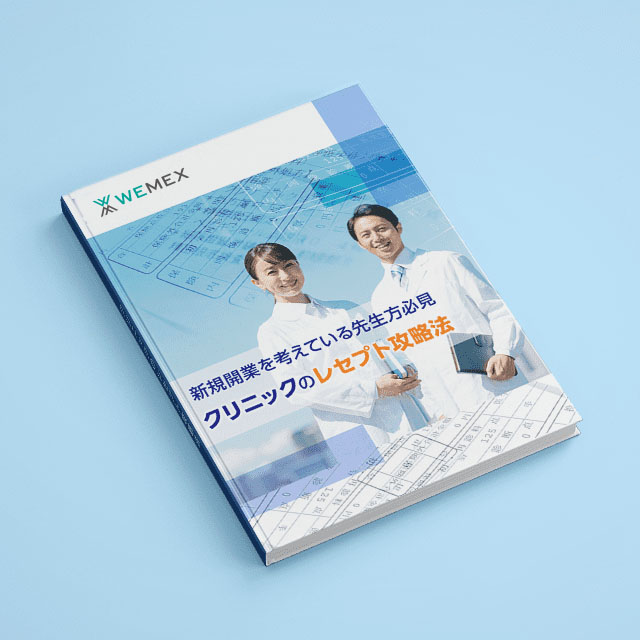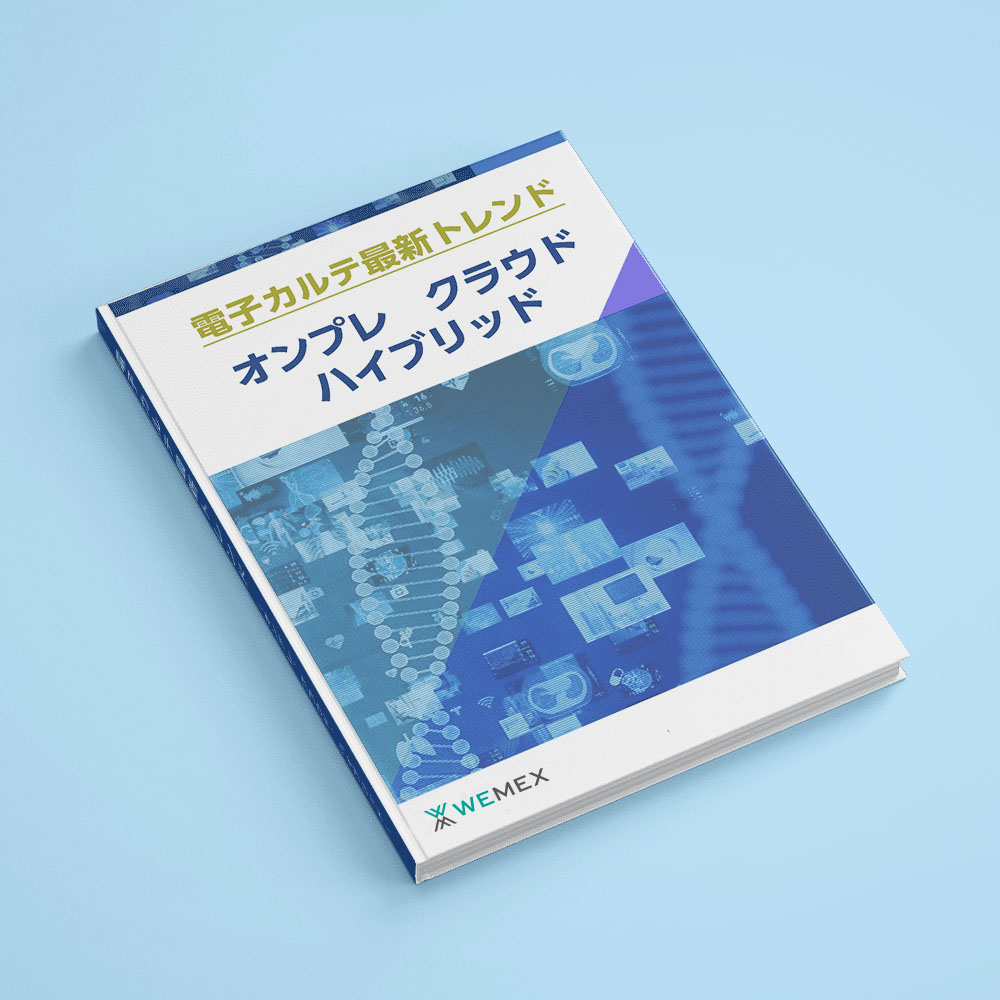#開業検討 #機器選定ポイント #紙カルテの電子化 #システム入替
目次
カルテ(診療録)の保存期間は5年だが…
カルテの保存期間は診療が完結した日から5年間であり、これは電子カルテも紙カルテも同様です。一方で近年の民法では、医療事故による損害賠償請求の消滅時効が20年となっているため、医療機関によっては20年間、もしくはそれ以上の期間にわたって保存するケースがあります。
損害賠償請求の消滅時効は医療行為をしてから20年間であり、被害者が損害賠償請求できることを知ったときから5年間です。医療行為から症状が現れるまでに5年以上かかるケースがあり、カルテがないと有事の際に対応できない場合があります。

出典:「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」(法務省)PDF
(https://www.moj.go.jp/content/001399955.pdf)
日本医師会の「医師の職業倫理指針【第3版】」によると、電子カルテは永久保存するべきという意見が出ています。なお、5年間保管するルールは、1957年に「保険医療機関及び保険医療養担当規則(第9条)」にて作られたものです。この時代は、電子カルテが一般的に普及していなかったため、電子化が進む現代には合っていないという意見が挙がっています。
出典:「電子カルテの保存義務の延長を求める要望書」(厚生労働省)PDF
(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001230851.pdf)
その他書類の保存期間について
医療機関で取り扱う書類には、医療法などの法律によって保存期間が規定されているので、保存期間内に破棄した場合、法律違反として罰則が科せられます。以下の一覧表を確認し、規定された期間分保存することを心がけましょう。
| 保存すべき期間 | 書類例 |
| 2年 |
● 病院・診療所または歯科技工所で行われた施術に関わる指示書 ● 病院日誌 ● 診療日誌(各科) ● 手術記録 ● 検査所見記録 ● X線写真 ● (病院の)入院患者・外来患者数を明らかにする帳簿 ● (特定機能病院の)紹介状 ● X線装置などの使用時間に関する帳簿 |
| 3年 |
● 歯科衛生士の記録 ● 調剤済み処方箋 ● (保険医療機関の)療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録 ● (保険薬局の)療養の給付に関する処方箋・調剤録 |
| 5年 |
● 助産録 ● 救急救命処置録 ● X線装置などの測定結果 ● 放射線障害発生するおそれのある場所の測定結果 |
出典:「法令上作成保存が求められている書類」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0624-5e.html)
紙カルテを20年保存するのは難しい
損害賠償請求の消滅時効は、医療行為を施してから20年間であるため、院内で保管できるような工夫をしなければなりません。
紙カルテを20年間分保存する場合、膨大な量になり院内の保管スペースの確保が必要です。比較的広い面積を有するクリニックであっても、20年間分の紙カルテを保存するのは困難といえるでしょう。また、紙の場合は経年劣化が生じるため、文字が薄れて確認が難しくなるリスクがあります。
また、カルテの保存を外部委託する場合、情報セキュリティの面で信頼できる業者を選定する手間が発生します。さらに委託費用が発生するため、クリニックによっては予算を調整できないケースがあるかもしれません。
クラウド型電子カルテが長期保管のハードルを下げる
カルテを長期間保存しなければならない問題に対して有効な手段が、カルテの電子化です。電子カルテを導入すると、保管スペースの問題が解消できるため、クリニック内の場所を有効活用できます。紙を電子化することで、劣化の心配がありません。また、業者に保存を委託する必要がなく、日々の運用で生じる紙のコストも削減できるため、経済的です。
電子カルテには大きく分けてオンプレミス型・クラウド型の2種類があります。いずれの種類も診療録の長期保管が可能ですが、オンプレミス型の場合は、院内にサーバーを設置しデータの管理や保存を行います。メリットとして、カスタマイズの柔軟性やセキュリティの高さなどが挙げられます。ただし、メンテナンスやバージョンアップを自院で対応する(もしくは、電子カルテメーカー担当に訪問してもらう)必要があります。
一方で、クラウド型の場合はサーバーがクラウド上に存在するため、メンテナンスやバージョンアップ作業を現地で対応する必要がありません。データは常にバックアップサーバーかクラウド上に保存されるため、災害時におけるデータ消失のリスクが少ないといえます。
また、両者のメリットを併せ持つ、オンプレ×クラウド型も存在します。これから電子カルテの導入を検討する際は、クラウド型・オンプレミス型のメリット・デメリットを比較し、電子化を進めましょう。以下の記事も参考にしてください。
>「電子カルテのクラウド型とオンプレミス型を比較!選ぶ際の比較ポイントを解説」
紙カルテを電子化する際に守るべきこと
紙カルテを電子化する際には、電子保存の3原則である「真正性」「見読性」「保存性」を守る必要があります。本ルールは、電子化したあとのデータにおいても遵守しなければなりません。
1999年に厚生労働省から通知された『診療録等の電子媒体による保存について』では、「電子媒体に保存する場合は次の3条件を満たさなければならない」とされ、カルテをデジタル保存する際に守るべきことを定義しています。これがいわゆる「電子カルテの3原則」と呼ばれるものであり、「真正性」「見読性」「保存性」を担保していない電子カルテは保険医療機関として、利用ができません。
(1) 保存義務のある情報の真正性が確保されていること。
○ 故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
○ 作成の責任の所在を明確にすること。
(2) 保存義務のある情報の見読性が確保されていること。
○ 情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
○ 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
(3) 保存義務のある情報の保存性が確保されていること。
○ 法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。
出典:診療録等の電子媒体による保存について(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1104/h0423-1_10.html)
なお、「保存性」については、「記録された情報が法令等で定められた期間にわたって真正性を保ち、見読可能にできる状態で保存されること」と定義されています。カルテを電子的に保存する場合は、保存性を脅かす原因としてコンピュータウイルスや障害などによる破損などが起きないように対策を図ることを求められているのです。
昨今、ランサムウェアなどにより電子カルテに障害が発生した事例が報告されていることもあり、医療機関に対してサイバーテロに対するセキュリティ対策が進められています。
電子化後の紙カルテは破棄するべきか
電子化後の紙カルテの保管は義務ではありません。しかし、カルテには患者名や住所、治療歴や家族歴などが記載されており、情報漏えいした場合プライバシーの人権侵害や医師法に違反するため、電子化後の紙カルテは破棄するクリニックが多いでしょう。
破棄には適切な方法をとる必要がありますので、外部業者へ依頼するなどがおすすめです。
まとめ
カルテの保存期間は、健康保険法では「カルテは完結から5年」と定められています。これは紙カルテでも電子カルテでも同じルールです。しかし、損害賠償請求の消滅時効を考慮すると、20年以上保管することが理想とされています。
電子カルテが主流となった現在では、半永久的に保管することが求められます。電子カルテについては、「真正性」「見読性」「保存性」の3原則をクリアしたものしか利用できません。
また、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」によると、保存性を確保するために外部・内部からの侵入による破壊などに対して、情報セキュリティ対策を徹底することが求められています。紙カルテの保管場所に苦慮している方は、電子カルテの導入・移行をご検討ください。